江戸幕府第11代将軍徳川家斉に関して分かっている
を中心に記載しております。
知っていても特に何かが変わるわけではない…けど、いつかどこかで何かに役立つかもしれない息抜き専用雑学としてご認識いただければ幸いです。
記事の中身をざっと見
徳川家斉の性格や特徴
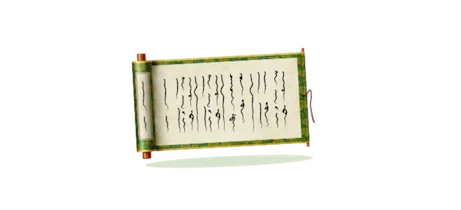
御三卿一橋家出身の初となる将軍
在任期間と子宝数歴代将軍No.1の2冠
父親には逆らえない
けど我は強い
超絶倫
あだ名オットセイ将軍
大の酒好きで女性好き
相当な酒豪
生姜好き
精力剤愛好家
権力好き
三国志好き
身体は頑丈で長生き
人に対しては温厚
など
徳川家斉の人物像を深掘り
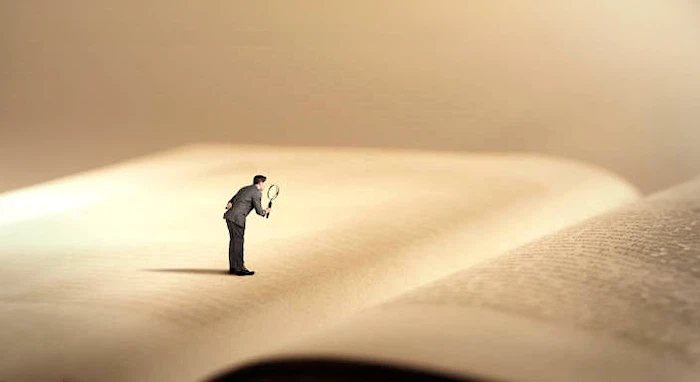
分かっているだけで
息子:26人
娘 :27人
の計53人以上もの子どもを授かった徳川家斉。

が将軍就任前半期のモットー。
政務関連は重臣の松平定信に任せっきりだったり、当時一橋家当主だった父・徳川治済の言いなりだった模様。
その憂れいがあったためか、将軍期の後半以降は自ら権勢を振るい大御所となった後も実権は握り続けることに。
権力や名声も割と固執するようになり

しております。
徳川家康、秀忠は将軍職以外のときに就任
晩酌を毎晩欠かすことなく、
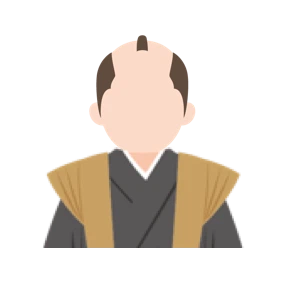
そうで相当な酒豪だったご様子。
生姜やチーズも大好きで、特に生姜は
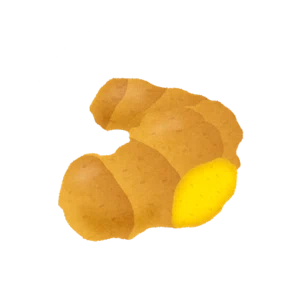
とされていたことから毎日食べていたそう。
(偏頭痛薬との見方も)
精力剤のお気に入りは、徳川家康も愛好していたとされるオットセイの局部を粉末にしたものでした。
そのため一部からはオットセイ将軍と呼ばれていたとか。
元来頑丈な身体のおかげか精力剤のおかげか、67歳まで生きたのは当時にすれば長生き。
江戸時代の平均寿命
45〜50歳
また、子沢山だったことから祝賀や養育費などで幕府の財政は確実に圧迫されていくも、徳川家斉自身割と豪奢な散財傾向がありました。
そのためか綱吉〜吉宗〜家治と続いていた庶民への締め付けも緩み、町人文化の代表ともされる
化政文化
が一気に華ひらき、国学や蘭学なども大いに隆盛することとなりました。
徳川家斉の女性関係 色恋事情

分かっているだけで53人もの子どもを遺した徳川家斉。
と同時に御三卿一橋家初の将軍でもあったことから、絶倫だったのは

で、

との見方も。
ただ、特に将軍期前半は政務そっちのけで子作りに励みすぎており、多い年で年間同時に3〜4人もの子どもを儲けていたご活躍ぶりは

との意見も多め。
正室との婚姻前に…

通例、正室とは婚姻を結んでから夫婦の契を交わすのが一般的だったのに対して

と婚姻前にもかかわらず手を出しているのが家斉流。
昼夜問わずお盛ん

徳川家斉のお盛んぶりを描いた浮世絵
夜は側室たちとダブルヘッダーをしていたり、それだけでは満足できなかったか
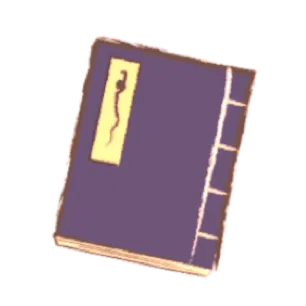
お盛んぶりも記録されております。
好きもの認定?

産まれながらか精力剤や生姜のおかげか、身体がとても頑丈だった徳川家斉。
ちょっとした病で倒れ命を落とすことも少なくなかった時代、特に病弱体質にある徳川家において徳川家斉自身は

だったそうで
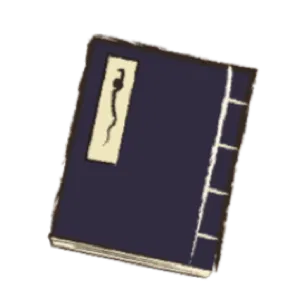
との記録が残っております。
ただ、別の史料には
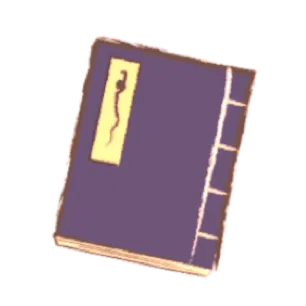
と普段から薄着でいた理由が…。
やはり好きものであったご様子。
東京大学の赤門

現在もある東京大学の赤門。
元は、子どもが多すぎて娘の嫁ぎ先全部を把握しきれなかった徳川家斉のために
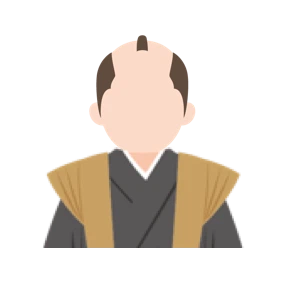
ことに由来しております。
そのため当時の江戸には朱色の赤門が点在しておりました。
今日残っている東大の赤門は、徳川家斉の21女・溶姫の嫁ぎ先となった加賀藩・前田家の屋敷門でした。
徳川家斉の性格や人柄が垣間見れるエピソード
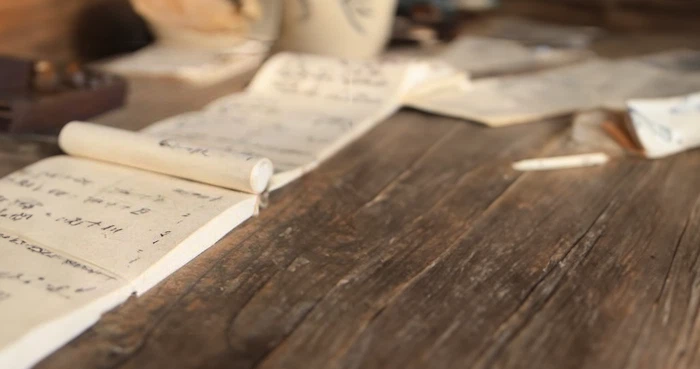
父・徳川治済には逆らえず、子どもを作ってばかりの絶倫将軍なイメージが先行がちながら、その性格は
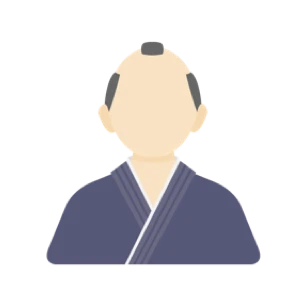
とされる徳川家斉。
そんな徳川家斉の性格や考え方などが垣間見れるエピソードをいくつかご紹介。
徳川家斉流人心掌握術

中国の三国志が大好きで何度も読み返していたそうな徳川家斉。
ある日、家臣たちと散歩中に寄った茶屋にて

と一言。
家斉の発言を聞いて凍りつく家臣一同。
その様子を見て笑いながら

とちょっとした自虐ネタを。
しかし、家臣は気を引き締める一因になったそう。
気持ちを汲める

飛鳥山での花見の様子を描いた浮世絵
桜の花見を毎年初夏に行っていた徳川家斉に対して、ある時家臣の1人が
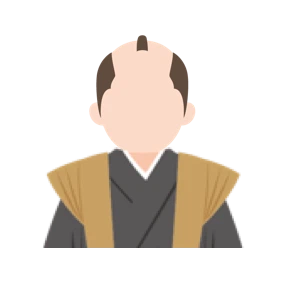
と徳川家斉に上申。
これを聞いた家斉、

だが、飛鳥山の桜は多くの庶民が楽しむところだ。
わしが行けば数日前から人の往来を禁じたりして、庶民の楽しみを奪う事になる。
と言い、続けて

と付け加えております。
徳川家斉の庶民を思いやる気持ちに、上申した家臣も大層恐れ入ったそう。
- 隅田川(の桜)
- 東京都墨田区〜足立区辺り
- 御殿山
- 東京都品川区
いづれも都内有数の桜の名所。
徳川家斉、菊を愛でる

ある時家臣たちに向かって

と一年程前に渡しておいた菊の根の話を持ち出した徳川家斉。
後日、豪華絢爛たる菊が続々と運び込まれる中、誰がみてもショボい菊が1輪。
その並んだ菊を見て家斉が一言。

正直なのはお前だけだ。
お前の菊を見ながら呑むぞ。
とそのショボい菊と持ってきた家臣を愛でたそう。
その家臣は後に天保の改革主導者となる水野忠邦でした。
父・徳川治済に対する思い

徳川治済
徳川家斉の将軍就任には父・徳川治済が表向きにも裏向きにも動いていたことを知ってか、

だった徳川家斉。
自身の将軍期前半に父・徳川治済が権力を欲しいままにしていたときも静観の構えを貫いており、顔色を伺う存在だったそう。
そんな徳川家斉の父・徳川治済に対する思いが伺えるエピーソードを最後に3つほど。
自分の誕生日

ある時家臣のひとりが
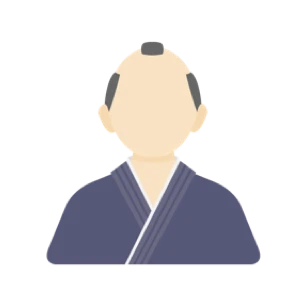
と言いまわっているの見た徳川家斉。
そんな姿を見て

と語ったそう。
徳川家斉の親を敬う気持ちが伺えるエピソード。
決して逆らわず

大の酒好きでかなりの酒豪だったとされる徳川家斉。
決して飲んでも飲まれなかったそうで、年々酒の量は増えていっていたとか。
そんな家斉を見た父・徳川治済がある時

と直接忠告しました。
以後、徳川家斉は

そう。
それからちょっと時が過ぎたある冬の鷹狩での時のこと。
あまりの寒さから全員が酒を飲み暖を取ろうとするも寒さは一向に和らがず…。
どんどんと飲む酒の量が増える面々。
そんな中、ある家臣が
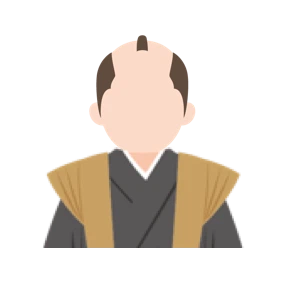
と徳川家斉に酒を勧めるも、

と冗談を言ってかわすばかりで結局3杯以上は決して飲みませんでした。
徳川家斉は何かを知っていた…?

初代・徳川家康の江戸幕府開闢以降100年以上経っていたためか、徳川家康への信仰も強くはなかったとされる徳川家斉。
徳川家斉将軍期は約50年と超長期政権ながら、先祖への法要行事である日光社参は一度も行っておりません。
が、徳川家斉にとって遠戚にあたり先代将軍・徳川家治の息子だった徳川家基の命日には、毎年欠かさず自ら参詣しております。
万が一徳川家斉自身が参拝出来ない時には、家臣を代参させるほどのご執心ぶりでした。
第10代将軍・徳川家治の長男で、幼少期よりとても聡明だったことから

と多くの家臣たちに目されていた人物。
将軍就任前に「家」の字を名前に賜るほど期待されておりましたが、18歳の若さで謎の死を遂げることに…。
徳川宗家の中で「家」の字を賜りながら唯一将軍になれなかったこともあり
幻の十一代将軍
と言われております。

ばかりか、

と見られており、且つ直系の血縁関係にあるわけでもない中でこのご執心ぶりは異例中の異例。
ただ、
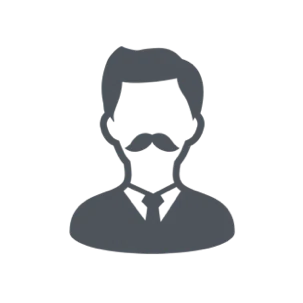
と指摘する歴史家も多数。
徳川家斉にとって
- 父・徳川治済はそうゆうことをし得る人物と見ていたこと
- 自分のために命を落としてしまった徳川家基への贖罪の意識
が垣間見える記録とされております。
徳川家斉の雑学的プロフィール

徳川家斉 肖像
出典:シーボルト著『NIPPON』
人物
- 生誕
- 1773年11月18日
- 旧暦:安永2年10月5日
- 星座
- さそり座
- 身長
- 約156cm
江戸時代の平均身長
155〜160cm
家系
- 氏族
- 徳川将軍家
- 血筋:一橋家
- 幼名
- 豊千代
- 父親
- 徳川治済
- 母親
- お富の方
将軍期間
- 就任時齢
- 15歳
- 在任期間
- 1787年〜1837年
- 天明7年4月15日〜
天保8年4月2日 - 在任年数
- 約50年
- 歴代順位
- 1位
- 徳川将軍家 在任期間ランキング
奥方
- 奥方数
- 17人(以上)
- 正室:1人
- 側室:16人
(一説には40人以上とも…) - 歴代奥方数
- 2位
- 徳川将軍家 奥方数ランキング
子ども
- 子宝数
- 53人(以上)
- 男子:26人
- 女子:27人
- 歴代子宝数
- 1位
- 徳川将軍家 子宝数ランキング
晩年
- 享年
- 67歳
- 死因
- 胃腸炎、腹膜炎
- 歴代長寿ランク
- 3位
- 徳川将軍家 長寿ランキング
江戸時代の平均寿命
45〜50歳
徳川家斉将軍期の主な世情
徳川家斉将軍期の主な施策
約50年の超長期政権
寛政の改革主導は松平定信
朱子学を正学とした寛政異学の禁を発布
大御所となった後も実権を握る
など
国内の主な出来事
本居宣長著
古事記伝が完成1798(寛政10)年
化政文化期1804(文化元)年頃〜
伊能忠敬が
大日本沿海輿地全図完成させる1821(文政4)年
シーボルトが長崎に鳴滝塾を開く1824(文政7)年頃
葛飾北斎が
富嶽三十六景を発表1829(文政12)年
歌川(安藤)広重が
東海道五十三次を発表1832(天保3)年
天保の大飢饉1832(天保3)年〜
など
徳川家斉将軍期の世界情勢
ジョージ・ワシントンがアメリカ初代大統領に就任1775(安永4)年
フランス革命が起こる1789(寛政元)年
ナポレオンが皇帝に即位1804(文化元)年
物理学者オーム博士が
オームの法則を発表1826(文政9)年
など
徳川家斉の次代将軍、先代将軍
当記事の参照や備考
一部個別に記載
掲載内容に関して
年代や星座等は基本的に新暦換算で記載しております。
年数や年齢は代による暦の違いや数え年の違いから、出典により±1〜3年の誤差がある場合もございます。
掲載画像はあくまで参考イメージとしてご覧くださいませ。
当記事は2022年末までに分かっている史料等や諸記事を元に記載しております。
今後見つかるかもしれない史料等によっては、全く違う内容になる可能性がある旨ご了承くださいませ。
参考文献など
※ 以下順不同敬称略
- 『徳川将軍列伝』著:北島正元版:秋田書店,1989/12/1
- 『徳川将軍家十五代のカルテ』著:篠田達明版:新潮新書,2005/5/16
- 『徳川十五代史』著:内藤耻叟版:新人物往来社,1985/11/1
- 『徳川名君名臣言行録』著:岡谷繁実、安藤英男版:新人物往来社,1981/1/1
- 『将軍の私生活』著:三田村鳶魚版:グーテンベルク21,2016/1/15
- 『骨は語る 徳川将軍・大名家の人びと』著:鈴木尚版:東京大学出版会,1985/12/1
- 『徳川将軍家墓碑総覧』著:秋元茂陽版:星雲社,2008/1/10
- 『上様出陣!―徳川家斉挽回伝』著:牧秀彦版:徳間文庫,2012/8/3
- 『遊王 徳川家斉』著:岡崎守恭版:文藝春秋,2020/5/20
- 『家斉の料理番』著:福原俊彦版:宝島社,2020/5/20
- 『近代日本の政治家』著:岡義武版:岩波現代文庫,2015/6/4
など他諸冊
徳川将軍家のご参考までに
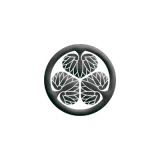 徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール
徳川将軍家 全15人の性格や特徴などをまとめた簡易プロフィール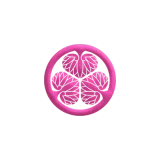 徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール
徳川将軍家 全15人のちょっとピンクな女性関係、色恋事情プロフィール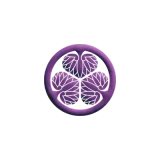 徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました
徳川将軍家 全15人を就任した順番に並べてみました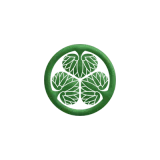 徳川将軍家 歴代在任期間ランキング
徳川将軍家 歴代在任期間ランキング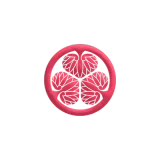 徳川将軍家 歴代奥方数ランキング
徳川将軍家 歴代奥方数ランキング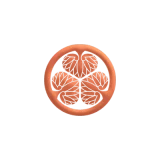 徳川将軍家 歴代子宝数ランキング
徳川将軍家 歴代子宝数ランキング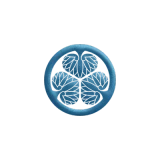 徳川将軍家 歴代長生きランキング
徳川将軍家 歴代長生きランキング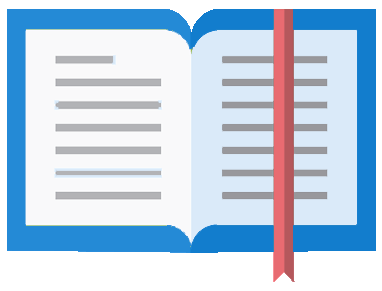 ダレトク雑学トリビア
ダレトク雑学トリビア 


現:東京都北区にある飛鳥山公園。
今日でも東京を代表する桜の名所のひとつとして人気があります。